火野葦平『糞尿譚』小論
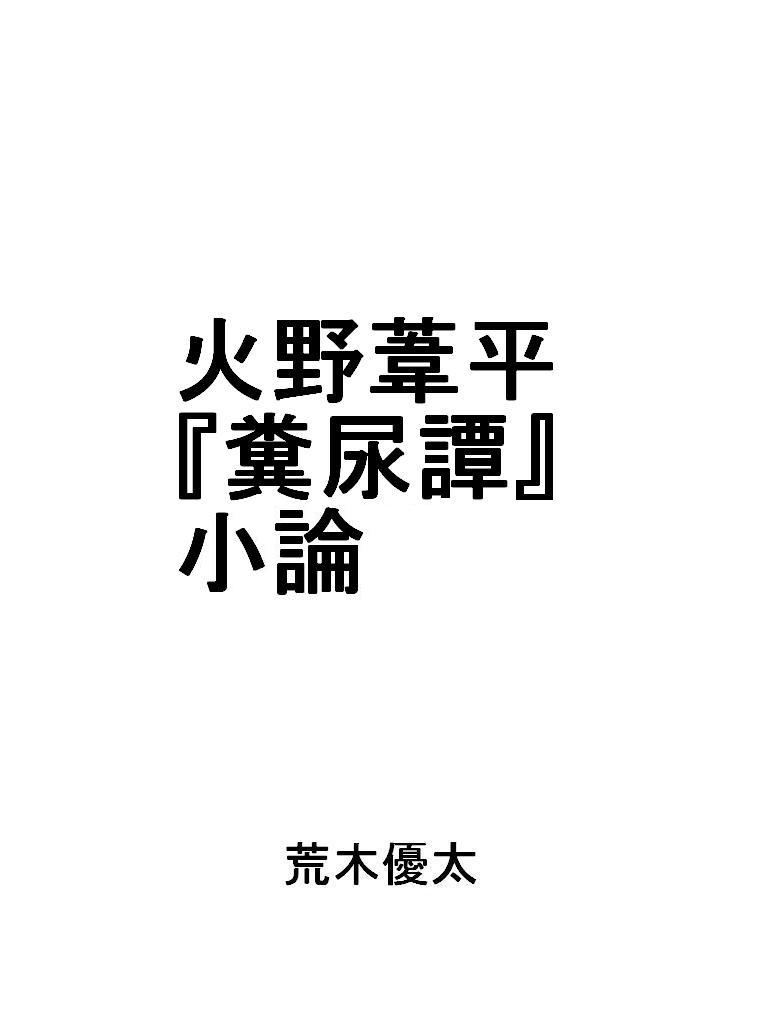
火野葦平『糞尿譚』小論
著:
荒木優太
| 状態 | 完成 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2012年10月01日 |
| ページ数 | PDF:8ページ |
| ダウンロード | PDF形式でダウンロード EPUB形式でダウンロード |
| Kindleで読む | New ※要設定 設定方法はこちら |
内容紹介
第六回芥川賞を受賞した火野葦平の『糞尿譚』は、近代的な糞尿汲取事業を主要なモティーフに描いている。事業を企てた元豪農だった主人公は、その事業においては自分で「糞尿」を使うことはせず、適切に市の糞尿を回収して、然るべき場所に配分することで、僅かばかりの賃金を得ている。彼にとって、糞尿とは貨幣(に交換する為)の貨幣だ。しかし、小説は彼に貨幣としての糞尿ではない別の側面を提供している。つまり、分配なり、貨幣なりに従属しない糞尿の価値だ。普段怒らない主人公は周りの人々から散々馬鹿にされた挙句、憤怒し、糞尿を撒き散らす最後の場面を力点として、糞尿の象徴性のずれを分析した。
【『糞尿譚』梗概】
『文学会議』、1937(昭和12)年10月に発表。小森彦太郎の家は代々続く豪農の家系だったが、彦太郎の代になって危機に瀕することになった。それは、所有していた山林などを抵当にして、市内の糞尿を処理する、糞尿汲取事業を彦太郎が始めたからだ。その仕事に一心になるばかりに、彦太郎は家族とも離れ離れに淋しく暮らす。そして、村の者からは卑俗な職業故馬鹿にされ「今に見て居れ」という執念のみが残り、ますます事業に専念する。閉鎖的な土地の党派的な政治性やゴミ処理を担当する部落民との確執など、彼の障碍は多いが、それでも自分の事業が市の公認のものとして認めてくれることを願って、少ない従業員と共にその仕事に従事してきた。しかし、最終的に彦太郎は仕事仲間から騙され、利益の権利の大部分を奪われてしまい、失意に陥ってしまう。
目次
| 一、貨幣の貨幣 |
| 二、「境界のあいまいさ」 |
| 三、長久命の長助 |
| 奥付 |
| 奥付 |