小林多喜二の代表論――『東倶知安行』から『蟹工船』へ――
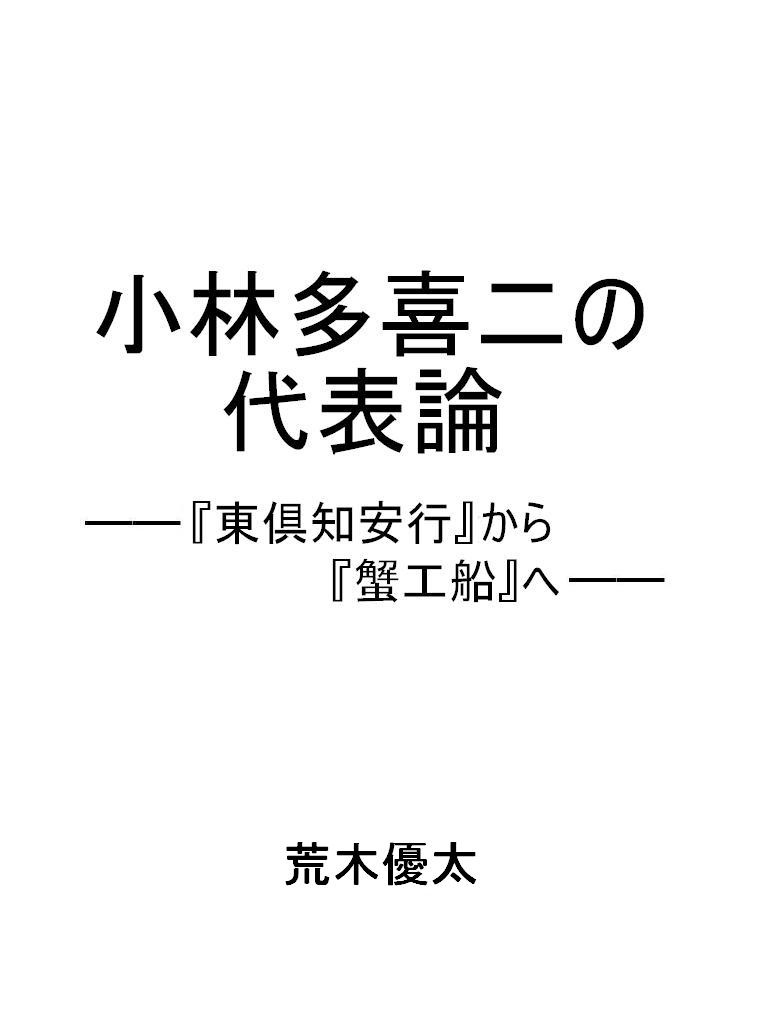
小林多喜二の代表論――『東倶知安行』から『蟹工船』へ――
著:
荒木優太
| 状態 | 完成 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2012年11月29日 |
| ページ数 | PDF:15ページ |
| ダウンロード | PDF形式でダウンロード EPUB形式でダウンロード |
| Kindleで読む | New ※要設定 設定方法はこちら |
内容紹介
小林多喜二には第一回普通選挙の応援経験に材をとった『東倶知安行』という短編小説が存在している。ルポルタージュとも評されるこのテクストは選挙という政治制度を背景に描いているために、組織の成員の「代表」が成立していく際に生まれる不可避的な構造を見出している。そして、その延長線上で日本プロレタリア文学不朽の名作『蟹工船』を読んでみると、『蟹工船』が『東倶知安行』の「代表」に関する問題設定を継承し、加えて部分的な応答をしようとしていることが分る。『蟹工船』でも『東倶知安行』と同型の問題性が見出され、しかも、部分的に代表の制度を回避しながら新たな組織が生み出されていく。必ずしも多喜二が意図していなかった「代表」というテーマを使って、二つのテクストは対としての読解を許す。そこで見出されるのが、小林多喜二の代表論だ。
【『東倶知安行』梗概】
『改造』1930(昭和5)年12月号に発表。語り手の「私」は普段は東京で銀行員をしながら、その裏では労働組合の仕事を手伝っていた。労働運動だけに集中できない自身に苛立ちながらも、今度行なわれる第一回普選で労農党から北海道で立候補する島田正策の応援に行くことになる。北海道につき、雄大な原始の自然の猛威に行く手を阻まれながらも、「私」とその仲間達は前進する。その先で出会ったのは、運動に専心するあまり、娘に生活の全負荷を負わせてしまっていた水沢という老人だった。その純粋な姿勢に「私」は胸をうたれる。
目次
| 序、「代議士をやめます」 |
| Ⅰ『東倶知安行』の代表論 |
| Ⅱ『蟹工船』の反代表論 |
| 結論、「代表」作としての『蟹工船』 |
| 註 |
| 奥付 |
| 奥付 |