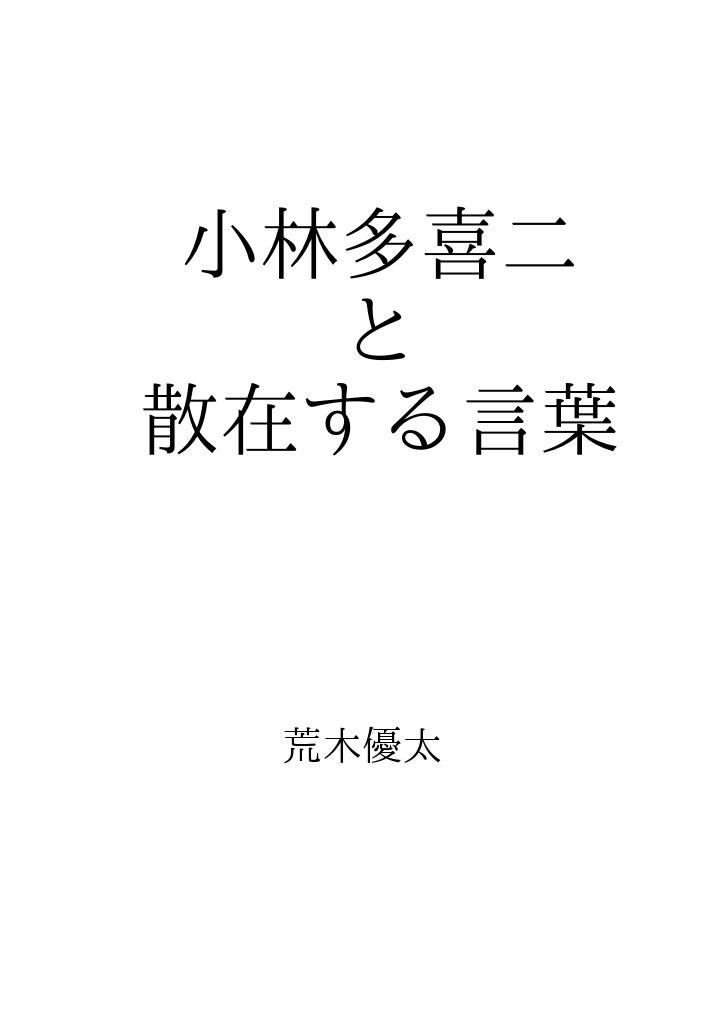内容紹介
小林多喜二のテクストに散見できる文字を支える物質性(本稿ではそれを文字環境と仮称した)に焦点を合わせながら、その様々な様態を分析した。そして、その文字環境に関する考察が多喜二の組織論とアナロジカルな関係にあることを明らかにし、多喜二文学の限界を考察した。
【多喜二略年譜】
1903(明治36)年 秋田県に生まれる。
1921(大正10)年 18歳。小樽高等商業学校に入学。『小説倶楽部』に短編小説の投稿を始める。
1924(大正13)年 21歳。商業学校卒業。北海道拓殖銀行に就職。
1927(昭和02)年 24歳。『万歳々々』を『原始林』(4月)に発表。
1928(昭和03)年 25歳。ナップ結成。ナップの機関紙『戦旗』創刊。『一九二八年三月十五』完成。『誰かに宛てた記録』を『北方文芸』(6月)に発表。
1929(昭和04)年 26歳。『救援ニュースNo.18.付録』を『戦旗』(2月)に、『蟹工船』を『戦旗』(5、6月)に、『不在地主』を『中央公論』(11月)に発表。
1930(昭和05)年 27歳。『一九二八年三月十五日』刊行。『工場細胞』を『改造』(5、6月)に発表。治安維持法で起訴、収監される。
1931(昭和06)年 28歳。日本共産党に入党。『オルグ』を『改造』(5月)に、『独房』を『中央公論』(7月)に、『テガミ』を『中央公論』(8月)に発表。
1932(昭和07)年 29歳。『沼尻村』を『改造』(4、5月)に、『党生活者』を『中央公論』(4、5月)に発表。
1933(昭和08)年 二月二十日、特高に捕まり、拷問、虐殺される。
目次
| 序論 文字環境について |
| 第一章 文字環境の本質的な可能性=散在可能性について |
| 第二章 文字環境の付随的な可能性①=欠損可能性 |
| 第三章 文字環境の付随的な可能性②=量産可能性 |
| 結論 散在する言葉/散在する同志 |
| 奥付 |
| 奥付 |