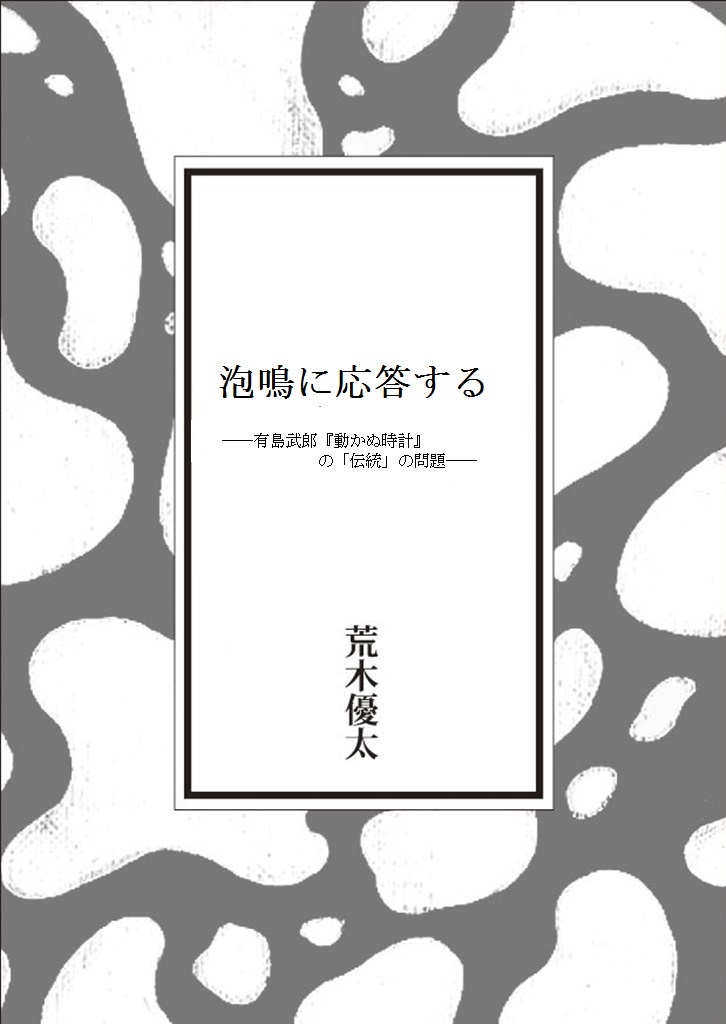大正七(1918)年一月、『中央公論』に発表された有島武郎の短篇小説『動かぬ時計』は同時代評は芳しくなく、研究者からもほぼ論及されることのない有島のマイナーなテクストにとどまっている。しかし、小説に先行する有島の評論文を参照してみたとき、そこには明治四三年と大正六年に発生した岩野泡鳴との論争の波紋を読み取ることができる。主人公、R教授はかつて海外の「国家学」を日本に輸入しようとしたが、その学説が日本的「伝統」と調和しないことを予感し、「伝統」に沿ったかたちでの受容を決意する。ここには泡鳴がその刹那主義評論とともに展開していた日本主義に対する応答がある。Rを泡鳴哲学に対する批評的形象として読むことで、小説にこめられた意味を明らかにしたい。
【目次】
一、学問と生活
二、有島武郎と岩野泡鳴(明治四三=一九一〇年)
三、有島武郎と岩野泡鳴(大正六=一九一七年)
四、〈学問‐伝統〉から脱落する〈生〉
五、「伝統」から「ミリウ」へ
【略年譜】
明治四三(1910)年 八月、「も一度「二の道」に就て」。一一月、泡鳴「断片語」。
明治四四(1911)年 二月、「泡鳴氏への返事」。
大正三(1914)年 一〇月、泡鳴『解剖学者』。
大正四(1915)年 一月、泡鳴の『筧博士の古神道大義』。
大正五(1916)年 一〇月、泡鳴『新日本主義』創刊。
大正六(1917)年 九月、『実験室』。一〇月、「芸術を生む胎」、『凱旋』。一一月、泡鳴「有島武郎氏の愛と芸術論」。一二月、「岩野泡鳴氏に」。
大正七(1917)年 一月、『動かぬ時計』。
大正九(1920)年 一月、「美術鑑賞の方法について」。四月、「美術鑑賞の方法について再び」。六月、『惜みなく愛は奪ふ』。