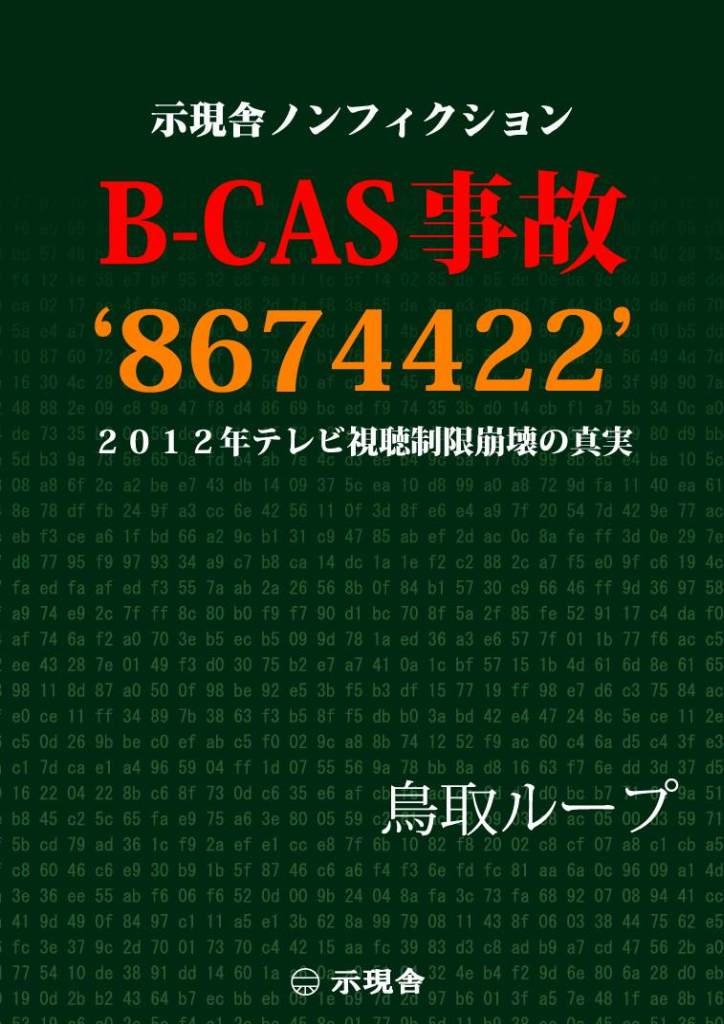内容紹介
2012年5月、デジタル放送の視聴制限を簡単に破るソフトウェアがネットで拡散され、おそらく何十万という世帯で有料放送の“タダ見”が可能になってしまうという前代未聞の事態が発生した。そして翌6月には警察による摘発が始まり、現在でも散発的に逮捕者が出ることが続いている。
しかし、なぜこのような「事故」が起こってしまったのか、比較的新しい知的財産権に関する法律と情報技術が関わる問題であるだけに広く理解されているとは言いがたい。
本書は筆者が1年にわたり当事者に対する取材と資料の分析を行い、その核心に迫ったものである。執筆にあたっては、できるだけ技術論を排して一般の人でも理解しやすくするように心がけた。一連の騒動は、法律と技術の関係とそれぞれの限界、そして知的財産権と情報技術のあり方を考える上で、重要な示唆を与えているだろう。放送業界のみならず、産業全般に関わる人々にもぜひお読みいただきたい一冊である。
目次
・本書について
●第1章 アナログからデジタルへ
●第2章 より便利なテレビを求めて
●第3章 丸裸にされたB-CASカード
●第4章 京都府警が動き出した!
●第5章 「事故」は防げたか?
●第6章 イタチごっこは終わらない
●付録
・安冨潔 慶応義塾大学法科大学院教授の意見書
目次
| 本書について |
| アナログからデジタルへ |
| 電波の発信と受信 |
| 電波の変調方式 |
| デジタル放送の仕組み |
| 手のひらの上で転がされるデジタルデータ |
| ソフトウェアとプログラムとソースコード |
| なぜB-CASが存在するのか |
| DRMが抱える矛盾 |
| 建前と実情 |
| 難視対策衛星とは |
| より便利なテレビを求めて |
| 工業国の側面 |
| 無名の有志らにより、さらに“研究”が進む |
| 暗号とは |
| B-CASで使われる暗号化方式とは |
| B-CASカードは何をしているのか |
| ソフトウェアの開発と発展 |
| B-CASカード解析の予兆 |
| “BLACKCAS” の衝撃 |
| 丸裸にされたB-CASカード |
| 謎の人物「ヤキソバン」 |
| B-CASカードの解析のために様々な人が参戦する |
| カードに見つかった「裏口」 |
| ついにカードの内部が暴かれる |
| CardToolの登場 |
| いかにしてB-CASカードは書き換えられたか |
| 「毒電波」が発せられる |
| SoftCASが実現した! |
| 宝探しゲーム |
| B-CAS社の損害は11億円以上 |
| 京都府警が動き出した! |
| 早朝の捜索と逮捕 |
| 京都地検と押し問答 |
| 淡々とした判決 |
| 裁判で争えなかった |
| 「平成の龍馬」氏 |
| 放送の受信は「人の事務処理」なのか |
| 慶応大学法科大学院教授・安冨潔氏の意見書 |
| 摘発の基準は? |
| 民事訴訟が提起される |
| 「事故」は防げたか? |
| B-CAS突破は防げなかったのか |
| 被害を拡大させた要因 |
| 松竹梅コース |
| カードが破られても有料放送の契約者数は減っていない |
| TRMP方式はB-CASの後継となるか? |
| イタチごっこは終わらない |
| 消えたサイトと、細々と続く開発 |
| 規制強化される一方で法律は穴だらけ |
| “公然の秘密”は保護されるべきか? |
| 規制が不可能な機器 |
| できるカードとできないカード |
| 付録 |
| おわりに |
| 安冨潔 慶応義塾大学法科大学院教授の意見書 |
| 奥付 |
| 奥付 |