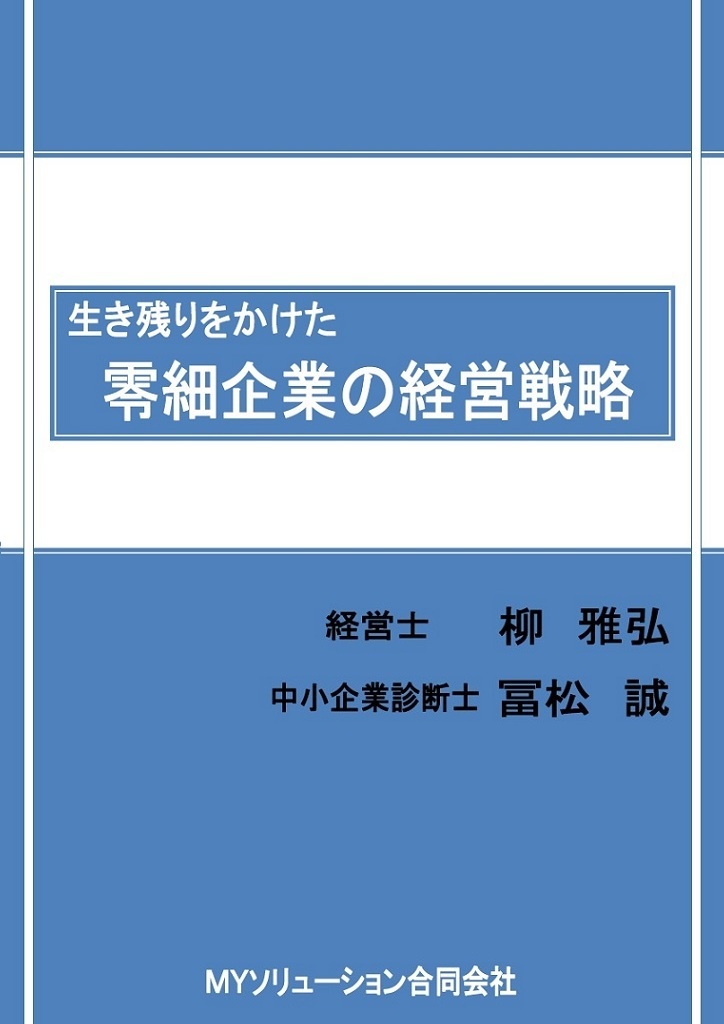私共のコンサルティングチームは、本質的な経営の改善を目指しています。すなわち、私どもがいち早く不要になるためにコンサルティングを行っているということが原点にあります。そして、悩める現代の経営者たちに何を伝えるべきなのか? 何故伝えなければならないのか? この二点について、議論を深めてきたわけです。時代の変化とともに、部分的に答えは変わり続けるでしょうが、本質的な原理原則は普遍だと考えています。
究極の答えは、利自利他の精神をもち人間好きであれ、の一言に行きつくに至りました。敢えて、私は無宗教だと付け加えておきます。人間とは生まれながらに善であるが、成長過程で悪をまとう弱い生き物だといえましょう。自己の利とは、他者の満足を与えた成果物だと仮定するならば、自己の悪しき心から開放されなければならないのです。
そして人間の成長過程で、悪しき心をまとうのが必然的となる教育制度のあり方に危機感を感じてきました。小中学校の大事な時期に、自らの頭で考え行動を起こす習慣を根付かせたいと願っています。中小零細企業の支援を通して、短期的な視点で人材の開発を行うとともに、学校教育の支援を通して、中長期的な人材の育成を推進していくことが私達の使命なのです。私達の夢は、まだ道程の途上ですが、踏まれてもなじられても折れない志は未来永劫に不変です。
その背景となるサラリーマン時代の視点、同じ経営者としての視点、支援者としての視点を、真逆の価値観を持つ2人の切り口から網羅的に書き下ろしました。答えとヒントを本書にちりばめましたので、経営改善の一端を担う一つの判断基準になれば幸いで御座います。
| はしがき |
| はしがき |
| はしがき |
| 序章 経済変化の波 |
| 序章 経済変化の波 |
| ■少子高齢化 |
| ■グローバル経済化 |
| ■生産性の低い日本 |
| ■個を殺す教育制度 |
| 1章 サラリーマンから見た会社 |
| 1章 サラリーマンから見た会社 |
| (1)組織風土は社長が作るもの |
| ■ビジョンと方向性が見えない |
| ■縦割り構造の弊害 |
| ■職人気質の教育制度 |
| ■拡散する会議 |
| ■合言葉は「気合や」 |
| ■そもそも仕事とは? |
| (2)社長と従業員は別の生き物である |
| ■人は認められたい生き物 |
| 情と知行は鳥の両翼 |
| 9千万円プレイヤーと1億円プレイヤーの違い |
| 人は話を聞いてくれる人を好きになる |
| ■目減りする会社の価値 |
| 御恩と奉公 |
| 御恩の大幅な目減り(給与カーブ) |
| 同じ職場にいる先輩が未来の自分だ |
| 2章 経営者同士の視点 |
| 2章 経営者同士の視点 |
| (1)業界と会社は違う |
| 看板を掲げていれば食べられる商売などない |
| 業界と会社は違う |
| ■自社のセールスポイントは |
| お客様のメリットを考えておく |
| ■経営計画の真髄は達成できないときにある |
| 計画は「現実的」にこだわる必要はない |
| 計画はチェックを行ってこそ初めて役に立つ |
| 会議は前向きに |
| (2)諸々の経営者勉強会 |
| ■勉強会 |
| ■学習することの本質とは? |
| (3)企業の類型 |
| 3章 支援者の視点 |
| 3章 支援者の視点 |
| (1)経営士としての主張 |
| ■失敗について |
| ■外注コンサルタントの種類 |
| (2)中小企業診断士としての主張 |
| ■ 良いコンサルタントとは |
| ■経営コンサルタントとしての信条 |
| 4章 零細企業の経営課題 |
| 4章 零細企業の経営課題 |
| (1)零細企業の経営課題 |
| ■「主体性」をもった経営体質づくり |
| ■組織的改善 |
| (2)解決のパーツ |
| 著者紹介 |
| 流浪人生たる生い立ち |
| 未来に向けてどう動くか |
| あとがき |
| あとがき |
| よいパートナーを |
| 奥付 |
| 奥付 |