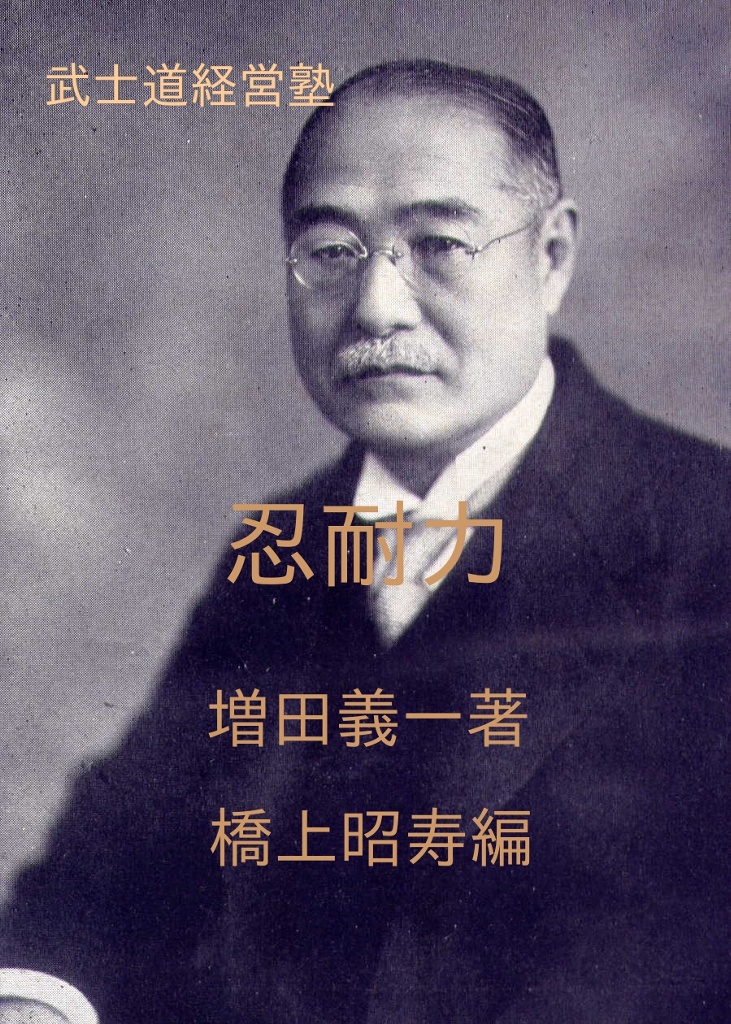内容紹介
事業経営というものは常に順風満帆のときばかりではない。時に思わぬ逆境の中に陥いる場合も多々ある。しかし私たちビジネスパーソンにはその困難な状況に耐え捲土重来を期するだけの強い精神力が求められる。世界中の成功者たちの足跡をたどってみると、その多くは自らの逆境を征服してきた人たちばかりである。本書では戦前の論客増田義一氏が国内及び海外の歴史上の数多くの偉人英傑たちの逸話を紹介しながら『いかにして境遇を支配し運命を打開するか』の心構えと方策について諄々(じゅんじゅん)と説いている。氏は『武士道』の著者である新渡戸稲造氏と共に実業之日本社を創設した人物である。そして数多くの著書をもって当時の青年たちに『新しい時代の社会人としての生き方』を指し示し、叱咤激励した。
目次
| 第一章 進んで難局に当たるの気概 |
| 年の暮れに煩悶する逆境者 |
| 逆境者は境遇を支配せよ |
| 人は鉄火の鍛錬により向上す |
| 災厄を逆襲するの意気 |
| 心の順境への道如何 |
| 境遇を征服し支配せよ |
| 環境を恐るるなかれ |
| 温室の花と野生の花 |
| 大石は激流をさかのぼる |
| 苦心惨憺たる努力を味わえ |
| 他人の体験が有力な参考 |
| 成功者の歴史は逆境征服史 |
| 百貨店王の体験教訓 |
| 心の持ち方とあきらめ方 |
| 忍辱も一つの修行 |
| 報恩のために侮辱を忍ぶ |
| 屈辱に遭って発奮す |
| 第二章 運命の開拓 |
| 運命を改造して進む人 |
| 運命とはなんぞや |
| 好運はどこにあるか |
| 人生常に行路難し |
| 人生はもと行路難 |
| 受難期の鍛錬 |
| 難関は登竜の門 |
| 難関に遭って泰然自若 |
| この試練の結晶を味わえ |
| 難局を切り抜ける人 |
| 進んで難局に立つ実業家 |
| 開運せる実業家の信条 |
| 運命開拓の鍵 |
| 運命開否の人物 |
| 稼ぐから生み出す子息四人 |
| 彼こそは青年発展の活教訓 |
| 第三章 行き詰まりはいかにして打開すべきか |
| 奮起勇進に必要な心理作用 |
| 前途の光明を発見せよ |
| 難関打開の要素 |
| 人生に必ず活路あり |
| 死中活あり大死一番 |
| 難関突破の根本力 |
| 進んで激務に従事せよ |
| 大業を成す者は底力の人 |
| わが国民は果たして底力あるか |
| 底力とはなんぞや |
| 底力ある者世界に優勝す |
| 底力の修養は現代の要求 |
| 底力は果たして修養されるか |
| 底力修養の三方法 |
| 第四章 弾力性の養成 |
| これら失敗の原因は何か |
| 自覚的の弾力性と他動的の弾力性 |
| 老人の発揮した弾力性 |
| 昔しのばれる会津気質の養成法 |
| 弾力性はいかに養うべきか |
| 第五章 失敗に処する態度 |
| 失敗に屈せざる弾力性 |
| 失敗に二種類あり |
| 失敗者より出でたる成功者 |
| 一時の失敗は成功する月謝 |
| 失敗時に取るべき決心態度 |
| 胆力修養と失敗の善用 |
| 第六章 希望は前途を照らす |
| 人生の光明は何か |
| 希望の光明なき者は発展せぬ |
| 逆境の間にも光明が望まれる |
| 希望と確信を持て |
| 光明を信じて疑わず |
| 目的の実現に努力する人 |
| 前途の光明はこれを己に求めよ |
| 光明を望む一秘訣 |
| 信念によって光明を見る |
| 暴風雨後の晴朗を思え |
| 太陽に直面せよ |
| 第七章 難局打開と信念 |
| 信念堅くして意志強し |
| 修養は実行より来る |
| 勝海舟の意志鍛錬法 |
| 学理上より見たる意志の力 |
| 些細(ささい)のことから着手せよ |
| 第八章 確信の力 |
| 全力を発揮せしむべき根本要素 |
| 成功の基は確信より来る |
| 確信は逆境を突破す |
| 確信する前に理知で判断せよ |
| 第九章 自信力の養成 |
| 成功の土台石となるもの |
| 事業に対する信念 |
| 信念強き者は外部の圧迫に抵抗す |
| 他人の言に動かされる人 |
| 動かぬ人はついに成功す |
| 毀誉褒貶に泰然自若 |
| 自信力ある者に煩悶なし |
| 自信力は決断力を生む |
| 第十章 決断力の修養 |
| 世上もっとも多く苦しむ問題 |
| 心に余裕ある人とない人 |
| 機会を知るもとらえられぬ人 |
| 成功者は決断力なきはなし |
| 心理学上に見た決断力の修養 |
| 決断力の乏しき原因とこれが矯正法 |
| 批評を恐れず思い切って行う習慣 |
| 男らしい態度を取る決心 |
| 第十一章 実行は最後の勝利 |
| 成功はみな実行のたまもの |
| 事業成功の原動力 |
| 一心不乱の力 |
| 精神力の修養法 |
| 第十二章 積極精神の涵養 |
| 積極精神とはなんぞや |
| 堅志奮闘の世界 |
| 敢為決行の勇者 |
| 積極精神の涵養法 |
| 第十三章 真剣味の偉力 |
| 記憶すべき成功五則 |
| 最善を尽くしてはじめて十分 |
| 名人の特長ここにあり |
| 一人の真剣なる力 |
| 英雄的気迫の第一特質 |
| 第十四章 いかにして目的を達成すべきか |
| 理想の目標 |
| 目的の単一化 |
| 目的の立て方 |
| 抱負を持つ人の強味 |
| 自信と自恃の必要 |
| 目的達成の第一要件 |
| ふつうの定石 |
| 決意断行と全力傾倒 |
| 心血を傾注する努力 |
| 信念は達成力の根本 |
| 信念は何から生ずるか |
| 執着力の強烈 |
| 艱苦に対する戦闘力 |
| 勝利への道 |
| 第十五章 進歩的人物の修養 |
| 目的の実現に努力する人 |
| 目的を真っ先に振りたてて進め |
| 自己の技量に満足せざる人 |
| 少年時代の心理で進め |
| 思い切って旧套を脱する人 |
| 熱心に研究する人 |
| 第十六章 準備の必要 |
| 徹底的に研究する人 |
| 信念の前に深慮あり |
| 準備を怠る者の結果 |
| 英雄豪傑が準備のために払った苦心 |
| 四十にして将来のために準備した銅山王 |
| 貯蓄は準備なり |
| 不時の将来に備える心 |
| 昔の武士は常に万一に備えた |
| もっとも安全な実業家の経営法 |
| 準備には内容の充実が必要 |
| 準備を心がける者の用意 |
| 第十七章 何事も先手を打て |
| 手遅れがちの人 |
| 優柔不断は機を逸す |
| 深く考え込みすぎるなかれ |
| 世の中は碁の先手争いか |
| 先手で強敵を辟易(へきえき)さす |
| 第十八章 事業と機先 |
| 機先と機知 |
| 一歩先への進み方 |
| 先が見える人 |
| 独創的思考の必要 |
| ヒントを得るに努めよ |
| 第十九章 何事も着眼第一 |
| 機会をねらえばつかみ得る |
| 商売にも急所がある |
| 世界一の小売商となった根本 |
| 鋭敏なる観察力の必要 |
| 第二十章 注意力の修養 |
| 完全の基礎は何か |
| 発明の動機と成功の秘訣 |
| 刮目(かつもく)すべき偉人の注意力 |
| 第二十一章 活眼の養成 |
| 成敗の分岐点は何か |
| 活眼とはなんぞや |
| 絶えず汝の四辺を見よ |
| 実業界における先見の明 |
| 商業能率増進の鑑識 |
| いかにして活眼を養成すべきか |
| 実物観察の効果偉大 |
| 根本は最善の努力 |
| 第二十二章 独創力の涵養 |
| 成功者は多く独創力に富める人 |
| 明日を知る人 |
| 断然トップを切る |
| 先見達識たる独創 |
| 大才を養う者は着眼遠大なれ |
| 新時代は創造力を要求す |
| 独創力の基礎的条件 |
| 研究が生んだ蚕業上の独創 |
| 原 著 者 |
| 原著者及び出典 |
| あ と が き |
| 武士と禅定 編著者 橋上昭壽 |
| 著 作 権(編集著作物) |
| 著 作 権 (編集著作物) |