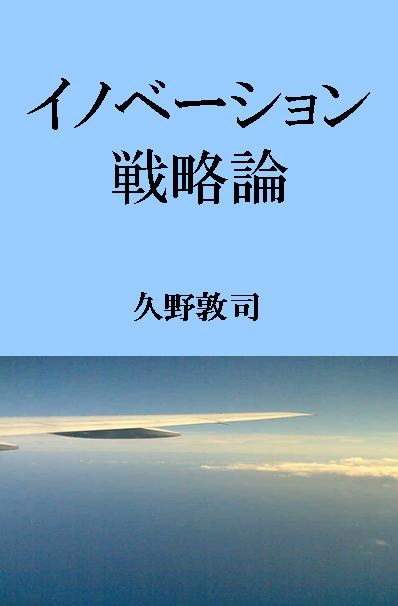内容紹介
本書は、新規事業の開拓活動に事業特許統合戦略の担当として参画した私が、イノベーションについて考察や実践した内容を、「イノベーション実践のフレーム」,「価値創造」,「新たな構造やプロセスのアイデア(発明)の創造」,「不確定性への挑戦」,「イノベーション実現組織に発生する罠への挑戦」という5つのテーマを中心に述べたものである。
目次
| 目次 |
| 目次 |
| 序 |
| 序 |
| 第1章 イノベーション実践のフレーム |
| 第1章 イノベーション実践のフレーム |
| 第1節 イノベーションの定義 |
| 第2節 イノベーションの中核(コア) |
| 第3節 イノベーション実践に必要な基盤条件の形成と6つの罠 |
| 第2章 価値創造 |
| 第2章 価値創造 |
| 第1節 価値,機能,技術の各表現形式 |
| 第2節 付加価値、知識、労働、マネー、権利と知的財産権 |
| 第3節 知識情報の最小単位 |
| 第4節 破壊的イノベーションの実践のための価値提供での着眼点 |
| 第5節 生産性と付加価値 |
| 第6節 顧客価値と顧客満足度、機能とコストの関係 |
| 第7節 独自の顧客価値提供をせずして、売り上げ向上を目指す者が陥る失敗 |
| 第8節 顧客価値実現とコア技術の関係 |
| 第9節 価値の根源である太陽光を受け取る人工光合成 |
| 第3章 新たな構造やプロセスのアイデア(発明)の創造 |
| 第3章 新たな構造やプロセスのアイデア(発明)の創造 |
| 第1節 発明は産業活動を通じて選択され、文明の中に集積する |
| 第2節 意味の実現原理と発明原理 |
| 第3節 発明の抽出と物理法則の抽出の類似性 |
| 第4節 発明の手法と数学での問題解決の類似性 |
| 第5節 基本発明を行なう方法 |
| 第6節 発明となるアイデアをふくらませる方法 |
| 第7節 発明の評価方法 |
| 第8節 出願が20年以上早すぎて特許権が切れた後に実用期を迎えた基本発明の活用 |
| 第4章 不確定性への挑戦 |
| 第4章 不確定性への挑戦 |
| 第1節 仮説と検証のサイクルを用いて不確定性に戦略的に対処する事が重要 |
| 第2節 不確定性の中で市場環境に適応するための事業・技術・知財の三位一体活動 |
| 第3節 社会と競合の中での創発的相互進化プロセスにおける業務 |
| 第4節 不確定性を伴う業務での業務効率の考え方 |
| 第5節 不確定性に伴うリスクを押し付けあう行動原理の組織の末路 |
| 第6節 「企画」が項目名称と予算額と時期だけの中身になりがちな原因 |
| 第5章 イノベーション実践組織の進化と技術進化 |
| 第5章 イノベーション実践組織の進化と技術進化 |
| 第1節 問題山積の連鎖による衰退を避けつつ、試練克服の連鎖による進化を図る |
| 第2節 予測能力と応用展開能力の修練によるイノベーション実践組織の進化 |
| 第3節 組織成長による、集中型→分散型→自律分散型という進化と階層上昇のパターン |
| 第4節 問題解決のための組織構築における方法論から組織へと、組織から方法論へ |
| 第5節 プラスのフィードバックループ構造を内包し、急速に進化する事業領域に注目 |
| 第6節 技術進化の法則の表現方法の1つ、発明グラフ構造 |
| 第7節 機能の組み合わせで相乗効果が発現する場合の仕組み |
| 第8節 20年前のSF映画と現在の対比から感じられる技術進化の法則 |
| 第9節 イノベーションを起点とした競争のレベルと変遷 |
| 第6章 イノベーションの促進要因 |
| 第6章 イノベーションの促進要因 |
| 第1節 イノベーション促進に必要な、壮大な課題、美しい解決策ビジョン、イノベータへの尊敬と優遇 |
| 第2節 上位概念が同一の新機能,同一機能の新型アーキテクチャでの実現にイノベーションのネタ有り |
| 第3節 開発テーマの触媒としての発明抽出行為 |
| 第4節 コンセプトオーガナイザー |
| 第5節 イノベーション活性化のための条件 |
| 第6節 イノベーション実現の現場 |
| 第7節 イノベーションオーガナイザ |
| 第8節 イノベーション創造モデルのレベル |
| 第7章 イノベーション阻害要因 |
| 第7章 イノベーション阻害要因 |
| 第1節 イノベーションキラー |
| 第2節 人材の問題発見能力と問題解決能力を蝕むマニュアル化と過剰管理 |
| 第3節 不適切な目標値設定はイノベーションを殺す |
| 第4節 イノベーション創造の一歩手前での停滞パターン |
| 第5節 人のモチベーションを損なう知的資産経営 |
| 第6節 知的資産経営と技術と志 |
| 第7節 アーキテクチャが作るイノベーションの檻 |
| 第8章 イノベーションのための組織 |
| 第8章 イノベーションのための組織 |
| 第1節 合理的な方法論の落とし穴 |
| 第2節 組織の構築の手順 |
| 第3節 社会が見せ始めた次の段階への飛躍の動き |
| 第4節 技術経営(MOT)と、プロジェクトX |
| 第5節 地域を活性化するイノベーションエンジン |
| 第9章 イノベーション実践組織に発生する罠への挑戦(管理と志、価値提供と対価獲得の調和) |
| 第9章 イノベーション実践組織に発生する罠への挑戦(管理手法と意識) |
| 第1節 意志決定ツールに潜む危険性 |
| 第2節 学問化の陥りやすい危険性と技術経営、知財学 |
| 第3節 過剰管理は知的貧困を招き、PDCAサイクルを知的貧鈍サイクルに変える |
| 第4節 稲の束と水田は、コア技術と特許戦略に似ている |
| 第5節 優秀発明者は人間組織を活性化する |
| 第6節 事業において、競争優位性の確保と大量普及を両立させる戦略(技術の困難度への対応が本質) |
| 第7節 市場拡大と事業利益拡大に、技術進化と市場拡大の速度と方向の各種制御手段の組み合わせが必要 |
| 第10章 日本のイノベーション戦略 |
| 第10章 日本のイノベーション戦略 |
| 第1節 日本のイノベーション促進のための政策 |
| 第2節 学生の構想力と問題設定能力増進が必要 |
| 第3節 日本国民の思考能力の危機 |
| 第4節 発明思考法を学校で学生に教えよう |
| 第5節 迫りくる日本の食糧危機に対処するのに必要なイノベーション促進策 |
| 第6節 株主資本主義を廃棄し、人と知的財産を大事にする人知資本主義に変革する事が必要 |
| 第7節 これからの日本の生きる道:世界インフラ産業立国 |
| あとがき |
| あとがき |
| 関連書籍の紹介と謝辞 |
| 著者紹介 |
| 発行 |