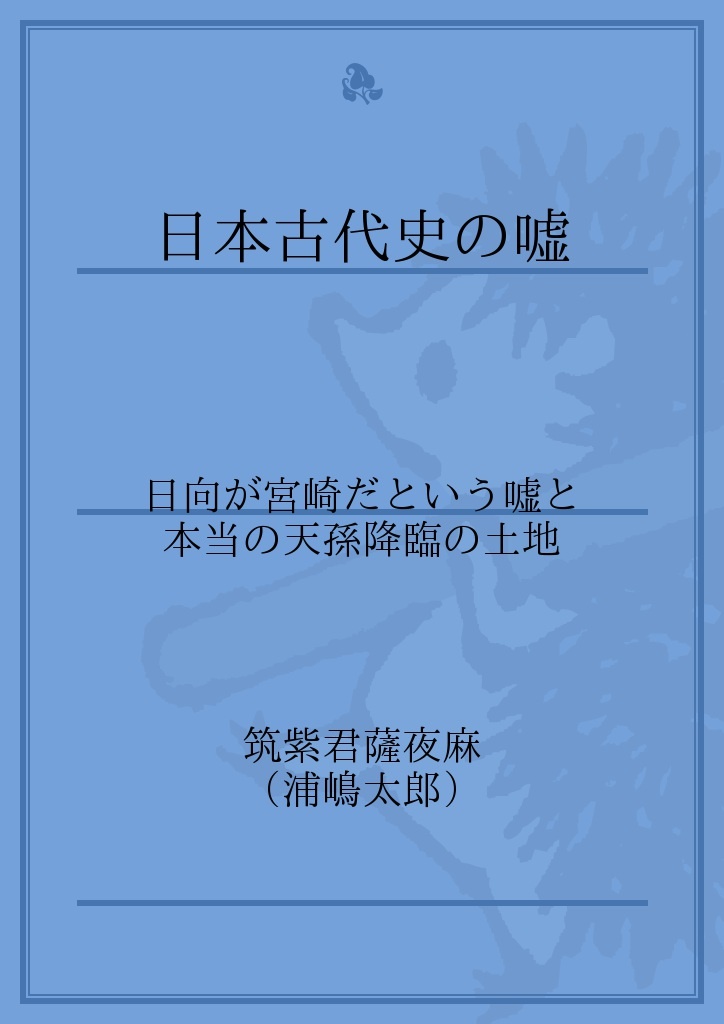内容紹介
今更、天孫降臨の土地が宮崎ではないとは口が裂けても言えまい。言えば準国家公務員という地位を失いかねない。
目次
| 第一章 『日本書紀』という国史 |
| 一、『日本書紀』の中身を知らない日本人 |
| 二、当時『日本書紀』を理解できたのか |
| 三、舎人親王を疑う |
| 四、「日本」を「ヤマト」と読む理由 |
| 五、白村江の戦いで滅んだのは倭国である |
| 六、天武天皇は日本に居なかった |
| 七、天武天皇は何処から来たのか |
| 八、天武天皇の事跡と年号 |
| 九、中大兄皇子という名の不思議 |
| 十、中臣鎌足(鎌子)と藤原鎌足は別人 |
| 第二章 『日本書紀』の創作 |
| 一、『日本書紀』は倭国の歴史を土台にして創られた |
| 二、神話の世界 |
| 三、天(アマ)の本当の意味 |
| 四、根(ネ)の本当の意味 |
| 五、磐(イワ)の本当の意味 |
| 六、三貴子(サンキシ 三人の王) |
| 七、記紀神話の常識という誤解 |
| 第三章 天孫降臨(テンソンコウリン) |
| 一、筑紫と日向 |
| 二、「天子降臨」ではなく「天孫降臨」という理由 |
| 三、船で到着しても天孫降臨という |
| 四、天孫降臨の土地を発見する |
| 五、天孫降臨した場所を丕基(ヒキ)という |
| 六、素戔鳴尊と大国主命と国譲り |
| 七、稜威之道別(イツノチワキ) |
| 第四章 神武東征(ジンムトウセイ) |
| 一、『日本書紀』のいう神武東征の本当のモデル |
| 二、神武東征の行程と宇佐 |
| 三、宇佐だけ詳しく書いてある理由 |
| 四、関門海峡を無視する習慣 |
| 五、安芸国 |
| 六、二人のハツクニシラス問題を解決する |
| 第五章 天照大神(アマテラスオオミカミ) |
| 一、伊勢志摩と怡土志摩(糸島) |
| 二、仲哀天皇と神功皇后 |
| 三、神功皇后の通った赤石(明石)は博多の博多湾にある |
| 四、天鈿女命(アマノウズメ)と珍彦(ウズヒコ) |
| 五、継体(ケイタイ)天皇と磐井(イワイ)の乱 |
| 六、天香山(アマノカグヤマ) |
| 七、「コノハナサクヤヒメ」と「かぐや姫」 |
| 八、藤原氏の為に創られた『竹取物語』 |
| 九、中臣と鎌足の本当の意味 |
| 第六章 浦嶋太郎の行方 |
| 一、山幸・海幸物語 |
| 二、浦嶋太郎と山幸彦と筑紫君薩夜麻 |
| 三、垂仁天皇が『日本書紀』の本当の主人公 |
| 四、白村江の戦いの前後を推定する |
| 五、「三種の神器」の行方 |
| 六、糸島は玉(ギョク)工房を持つ大王の故郷 |
| 七、高木神(タカキノカミ) |
| 第七章 江田船山古墳 |
| 一、古墳の盗掘と破壊 |
| 二、石舞台の謎 |
| 三、江田船山古墳とは |
| 四、江田船山古墳発掘をめぐる一部始終 |
| 五、江田船山古墳の本当の持ち主 |
| 六、「船山」の意味 |
| 七、銀象眼銘大刀の銘文 |
| 八、銀象眼銘大刀の絵 |
| 九、浦嶋太郎(山幸彦)は国造(コクゾウ)である |
| 十、高句麗と江田船山古墳 |
| 第八章 我々の思い込み |
| 一、漢音と呉音 |
| 二、「倭人の存在」を隠す『日本書紀』のとった手段 |
| 三、熊襲国は何処にあったのか |
| 四、日本古代史の謎説き |
| 五、咋(クイ)は喰(クイ)や杭(クイ)ではない |
| 六、神社の施設は古墳をモデルに作られた |
| 七、この土地を江田という理由 |